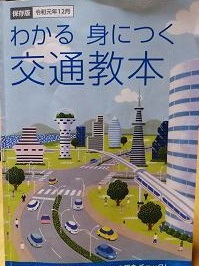こんにちは!
シニアライフを探求するシニアブログのチム(@tikao2440)です。(^▽^)
シニアの60代最後の免許更新お知らせが届きました。
心身の衰えとともに自動車を安全に運転することへの悪影響はないのか、
法令上は、70歳から講習の内容が変ってきます、75歳から講習の合理化、高度化と認知機能検査が実施されます。
他人に迷惑を掛けないことを人生の心情としている私ですが、事、自動車事故に関しては注意をしているつもりでも若いときと比べるとその反射神経の衰えは認めざるをえません。
そのリスクを最大限軽減するために、シニア・高齢者は免許更新にあたって今一度、自分の運転マナーを見直し、心構えを新たにする意味で記事として取り上げることとしました。
今年度の交通事故ワースト
以下、警察庁発表の数字を引用しています。
今年の8月16日までの死亡事故は、
1.愛知県 90人 前年比 +7人
2.神奈川県 88人 前年比 +2人
3.東京都 86人 前年比 +21人
全国の死者数: 1,641人 (前年比: -135人)
高齢者死亡事故の特徴と要因
前記の死者数は,高齢者を含め全年齢層で減少傾向にあるものの,高齢者人口自体が増加しているため,死者数に占める65歳以上の比率(高齢者)が70%以上に増加している。
その要因としては、
・高齢化による高齢の運転免許保有者の増加
・加齢に伴う高齢者の身体的特性(年齢が高くなるにつれ法令違反が多くなる(直前直後横断、
横断歩道以外横断等、自転車の一時不停止や信号無視等))
などです。
今回は、主に免許更新時の運転者側の立場の心構えではありますが、前記死亡者は、歩行時、自転車走行時も含まれます。
歩行者や自転車走行者の交通違反によって死亡しても、相手側は悲劇な思いに駆られるのです。
川崎警察署の待合椅子の前に掛けられた掲示板には、渋谷の人身事故、「家族は未来を奪われてしまった」という見出しの新聞記事が貼られていました。
当時、ブレーキとアクセルの踏み間違いという高齢者の運転ミスによる死亡事故に衝撃を受けて、「ブログを始めるキッカケ」にもなりました。
最近の道路交通法令の改正点
一部、関連事項を抜粋して取り上げます。
1.携帯電話使用等(ながらスマホ)対策
・罰則の強化(交通の危険、保持)
事故に繋がるようなスマホの操作
・運転免許の仮停止(人身事故)
事故を起こして人を死傷させた場合
2.高齢者対策
・臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
・臨時適正検査制度の見直し
・高齢者講習の合理化・高度化
3.準中型免許の新設
車輌総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できる。
4.「あおり運転」に態様する場合、免許停止処分
高齢者の免許更新と課題
警察庁によれば,平成28年に運転免許証の更新の際に認知機能検査を受けた75歳以上の高齢者約166万人のうち約5.1万人は認知機能が低下し認知症の恐れがある第1分類と判定されているそうです。
前述した高齢者死亡事故の要因として、高齢運転者の特性をのべましたが、
年齢や体力,過去の経験等によって大きな個人差が認められるものの,一般的に,
・視力等が弱まることで周囲の状況に関する情報を得にくくなり,判断に適切さを欠くよう
になること・反射神経が鈍くなること等によって,とっさの対応が遅れること
・体力の全体的な衰え等から,運転操作が不的確になったり,長時間にわたる運転継続が難
しくなったりすること・運転が自分本位になり,交通環境を客観的に把握することが難しくなること
などが挙げられており,これらの特性が,75歳以上の運転者が死亡事故を起こしやすい要因の一つになっているものと考えられる。
出典:内閣府
高齢運転者による交通死亡事故の人的要因として、75歳以上の運転者は、ハンドル等の操作不適による事故が最も多い車輌単独事故(工作物追突や路外逸脱)、次いで内在的前方不注意(漫然運転等)、安全不確認などが挙げられます。
身体的対策
このブログでもシニアの運動不足対策として、下記のような記事を紹介してきましたが、
加齢による筋力の衰え、身体機能の変化を維持向上するにはこれ以外にはありません、
日常の買い物、ドライブを楽しみたいのであれば、75歳以上の認知機能検査を通過するために、無駄な時間とは思わず努力するしかないと自分に言い聞かせます。
認知機能対策
軽めの認知症についての対策を考えたことはありませんが、有効で効果ある対策を実行できればいいかと思います。例えば
まとめ
最後に高齢者が起こす最も多い事故を再確認し、改めてその対策と動機付けをしたい。
1.ハンドル等の操作不適による事故は、スピードを出さない、カーブではスピードを落とす、
片手運転をしない、車内の珍事に目を奪われない、スマホに対応しない、水分の補給は車を
止めて、など、
2.漫然運転等による事故は、集中力や注意力が低下して、他の車や歩行者・信号などに気付く
ことができず事故を起こしてしまう。どんな時にボーっとしたり考えごとをしたりするか、
悩みや不安に陥っているとき、寝不足が続き疲れきっているとき、持病の薬を服用中、助手席
から話しかけられるときなど、
3.安全不確認が多い事故は、急いでいるとき、思い込みが強い、視野が狭い、徐行運転をして
いない、安全な道路を走っていない、交差点の危険度を認知していない、予測運転ができて
ないなど
予測できることを確認することで、ある程度対処できる。事故が起き易い場所、カーブや交差点、
十字路、見難い横断歩道など事故発生確率が低い道路を選択して走行するようにする。